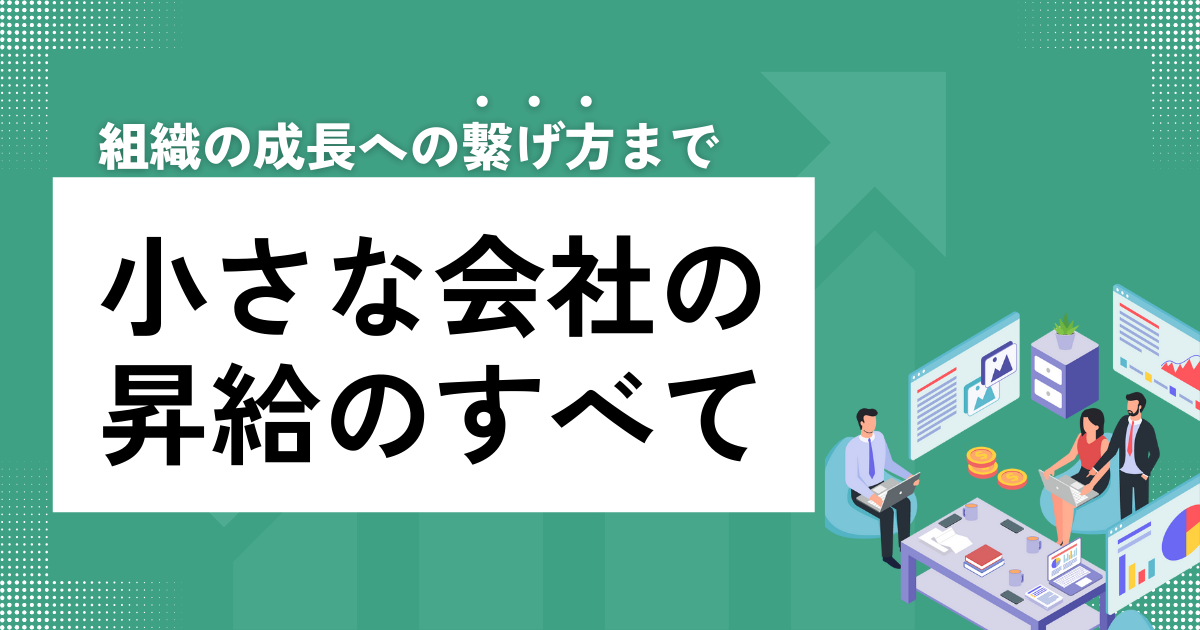昇給について気になる経営者の皆さん、理解しておくべきポイントが盛りだくさんです!
一番理解していただきたいポイントは、会社の成長のために昇給を戦略的に活用すること。
社員が最も関心のあることは、自分と家族の生活の安定と向上です。決して会社の成長ではありません。
だからこそ、昇給の原資が会社の利益であることを教育することから社員の行動が変わり始めます。
さらにこの記事では、昇給制度の違いや計算方法など、知っておくべき情報を丁寧に解説していきます。
具体的には、昇給の意味や達成目標、日本の企業で主流な昇給制度、年齢別昇給額の相場、ベースアップと昇給の違い、年次昇給調査と現状、企業別昇給制度の事例紹介、昇給額や昇給率の計算方法、注意点やまとめなどを取り上げます。
この記事を参考に、自社の昇給制度をより効果的に活用し、従業員のモチベーション向上や人材育成に役立てていただけると幸いです。さあ、詳しく見ていきましょう!
昇給
昇給の戦略的活用
昇給とは、企業が社員の給与を引き上げる制度のことです。賃金水準の向上は、社員と家族の生活の安定と向上に繋がります。私は、「社員の生活水準を上げる」ことは、小さな会社の会社の目的に掲げることだと考えています。その事例をたくさん見てきた経験から、この考え方が浸透できたときに全社一丸体制が始まります。
昇給原資は利益です。この当り前のことが社員の中に根付くと、社員は利益に興味がわきます。例えば、毎月会社の数字を社員に公開すると、売上から経費を引いたものが利益だと分かります。今まで、売上が増えるると「労働時間が伸びる!」とクレームを言っていた社員が、売上が増えたら喜ぶようになったり、社員教育や部下へのフィードバックに興味がなかった上司が、社員退職に伴う莫大な採用費に気付くと、社員が退職することに興味を持つようになります。売上を増やすことや経費を減らすことは経営者なら当たり前のことですが、社員にとってはそうではないのです。昇給はその当たり前のことを教育する最高のツールです。だからこそ、会社の数字を社員に教育して、社員の当たり前基準を上げて下さい。そのスイッチが入らないと、自分事にはなっていないため、どんな制度やツールを入れても空回りします。昇給からすべての改善は始まります。
経営者の人間的信頼に繋がる
企業における昇給の機能とは、社員のモチベーション向上や、定期的な人事評価を通じて能力や業務遂行に対して適切な報酬を提供することです。しかし、経営者が昇給の目的として考えるべきは、労働者の生活水準の向上や安定と考えるべきです。社員は会社の成長よりは、自身の生活の安定と向上を求めています。経営者がその言葉を発することで、社員からの人間的信頼を得ることに繋がります。経営者が社員から人間的信頼を得ることは、あらゆる事業活動が円滑に進む原動力になります。結果として、経営者から「社員が俺の言うことを聞かない。」という発言はなくなっていきます。社員が会社方針に懸命に取り組む風土が生まれれば、社員一人ひとりが成長し、仕事への貢献度が向上します。経営者が社員第一を標榜するだけで、社員がスキルアップや職務拡大を目指し、企業に貢献する意欲を持ち続けられるようになっていきます。
「昇給の原資は何でしょう?」と社員に質問して下さい。答えは、「利益」です。ここで初めて会社利益が自分事として考えられるようになります。多くの小さな会社の経営者が、「社員が会社利益に興味を持たない」といいます。昇給と利益・売上・経費節約すべてが一気通貫で繋がります。昇給は社員が最も関心のある項目であり、社員教育に使える材料にもなります。最大限この材料を生かしてください!
昇給制度の分類と特徴
昇給制度は、大きく分けて「定期昇給」と「能力給」の2つに分類される。定期昇給は、一定期間ごとに自動的に給与が増加する制度であり、勤続年数や年齢に応じて昇給が行われることが多い。一方、能力給は、社員の業務遂行能力や成果に応じて給与が引き上げられる制度である。
それぞれの特徴は以下の通り:
– 定期昇給: 給与が一定の割合で増加し、年功序列に基づく昇給が行われる
– 能力給: 社員の役割、業務成果やスキルアップに応じて、個別に給与が調整される
企業は、社員の役割、能力や貢献度に応じた適切な昇給制度を選択し、運用することが重要だ。
定期昇給と能力給の違い
定期昇給と能力給の違いは、前者が一定期間ごとに自動的に給与が増加する制度であり、勤続年数や年齢に応じて昇給が行われるのに対し、後者は社員の業務遂行能力や成果に応じて給与が引き上げられる制度である。能力給は、社員の働きに応じた報酬を目指す制度だ。
日本の企業での主流な昇給制度
日本の企業において主流な昇給制度は、年齢や勤続年数による昇給と、職務内容を評価した昇給の2つ。
年齢や勤続年数による昇給は、年功序列制度が背景にあり、従業員が安定して生活できることが狙い。
一方、職務内容を評価した昇給は、従業員の能力や業務遂行能力を重視し、個々の社員が自己管理できるよう育成。
しかし、経済状況の変化や労働市場の多様化に伴い、企業は様々な昇給制度を取り入れつつある。
例えば、定期昇給や年次評価制度、能力給制度など。
これらの制度は、昇給額や評価基準が異なり、従業員のモチベーション向上や人材活用の目的がある。
最近では、小さな会社もこうした昇給制度を導入するケースが増えている。
年齢別昇給額の相場
年齢別の昇給額の相場は、高卒・大卒別や部下を持つ立場になることで異なる。
高卒者は、20代の前半で月例6000円、後半で7000円、30代で8000円、40代で9000円程度。
一方、大卒者は、20代前半で月例8000円、後半で9000円、30代で10000円、40代で11000円程度。
部下を持つ立場になると、昇給額はそれ以上になることも。
ただし、これらはあくまで一般的な相場であり、企業や業界によっては異なる場合もある。
ベースアップと昇給の違い
ベースアップと昇給は、両者ともに労働者の賃金が引き上げられる点では同じだが異なる概念。ベースアップは、組合や企業の労使交渉で取り決められる全従業員の基本給を一律に上げる案であり、経済指標や物価上昇に対して労働者の生活を守る目的がある。
一方、昇給は、基本給以外に加算される給与要素で、年齢や勤続年数、職務内容、業績などを考慮した個別の従業員の賃金アップを指す。昇給は、労働者の働きぶりを評価し、努力や成果に対して報いる目的がある。
要するに、ベースアップは全員に適用される一方で、昇給は個々の労働者の業績や能力によって異なるため、両者の違いが生じる。
双方の計算方法と効果
ベースアップの計算方法は、全従業員の基本給に一律で加算される金額を決定する。
例えば、企業が全従業員に対して3%のベースアップを実施する場合、各従業員の基本給に3%を加算した金額が新しい基本給になる。
一方、昇給の計算方法は、年齢や勤続年数、職務内容、業績などに基づいて個別に加算される金額を決定。
昇給額は、企業や従業員の規模、業種、業績などにより異なる。
効果として、ベースアップは労働者全員に対する賃金の引き上げを行い、購買力の維持や生活水準の向上に効果がある。
一方、昇給は働きぶりを評価し、労働者にモチベーション向上や成果に見合った報酬を提供することで人材の定着や育成に効果がある。
年次昇給調査と日本の現状
日本では、年次昇給制度が広く普及しており、勤続年数や年齢に応じて給与が自動的に増加することが一般的です。しかし、近年の労働市場の変化や経営環境の悪化に伴い、従来型の昇給制度が見直される動きが見られます。
年次昇給は、昇進や昇格に伴う賃金の引上げではなく、一定の業務遂行能力があることを前提として、毎年一定額の基本給を増やす制度です。定期的な人事評価に基づいて実施され、社員の労働意欲を高める効果が期待されます。
しかし、これらの制度は、実績や能力に応じた給与体系とは異なり、勤続年数や年齢が給与水準に大きく影響するため、年功序列型の給与体系と批判されることもあります。そのため、中小企業においては、業績や能力に応じた昇給制度への移行が求められるケースが増えています。
高卒と大卒の昇給額の違い
高卒と大卒の昇給額には、一般的に大きな違いがあります。これは、高卒者は基本的に大卒者よりも低い給与水準からスタートするため、経験や能力に応じて段階的に昇給していく制度が主流となっています。
一方、大卒者は高卒者よりも高い初任給からスタートすることが一般的であり、昇給額も高卒者に比べて大きくなっています。これは、大卒者がより高い専門知識やスキルを持っているとされることや、企業が大卒者を長期的な人材育成の視点で採用していることが影響しています。
しかし、昇給額には個別の企業の制度や経営状況によって差がありますので、高卒・大卒に関わらず、自社の制度や市場の動向を把握し、適切な昇給制度を検討・導入することが重要です。
企業別昇給制度の事例紹介
企業によっては、昇給制度を独自に設定・運用している事例があります。たとえば、一部の企業では、「能力給」を導入し、社員のスキルや業務遂行能力に応じた昇給を実施しています。
また、「目標管理制度」を導入した企業では、社員に個別の目標を設定し、その達成度に応じて昇給額が決定される仕組みが採用されています。この制度は、社員自身が自分の業務成果を明確に把握し、昇給の根拠を理解しやすいというメリットがあります。
さらに、最近では、「賞与と昇給の分離」に取り組む企業も増えており、一定の業績を超えた場合には、特別な賞与を支給することで、社員のモチベーションを高める制度が導入されています。
これらの事例を参考に、自社の経営状況や人材育成のニーズに合わせて、適切な昇給制度を設計・運用することが、企業経営において重要なポイントとなります。
育成や成果に応じた昇給制度
育成や成果に応じた昇給制度は、企業が人事評価や社員の能力や業務遂行の成果を考慮して、賃金の増加を行う方法である。一般的に、年齢や勤続年数による定期昇給や昇格・昇進とは異なる制度だ。従業員の労働力増強に主眼を置き、以下のようなポイントを採用する。
– 人事評価に基づく能力別昇給
– 成果報酬制度
– 職務内容に応じた職務手当
日本では年功序列型の昇給が主流だが、中小企業や若手社員の多い企業では成果主義を採用するケースも増えている。企業によっては、大卒と高卒の新入社員の給与に差を設けず、育成や成果によって昇給を決定する制度を導入している。
しかし、行き過ぎた成果給は、大部分を占める普通の能力しか持たない社員のモチベーションを奪う。理由は、結局大多数の社員は特別な能力を持っていないため、大きな成果は得られずにやる気を失います。それよりは、給与は社員生活を維持するものと考えて、子供の教育費にお金がかかる世代や家族構成などを考慮して給与体系を考えるべきです。結果として、大多数の社員が安心できる働け、途中で退職する社員も少なくなり、会社のことを愛してくれる社員が増える結果に繋がります。
賞与を利益の分配ととらえて、大きな成果を上げたものに大きく分配してください。
昇給額や昇給率の計算方法
昇給額や昇給率の計算方法は企業によって異なるが、以下の3つの要素で構成されることが一般的だ。
1. 基本給のベースアップ
給与の基本部分である基本給を一定の割合で引き上げる。物価が上昇しているときは、社員の生活水準を維持するために重点的に配分する必要があります。
2. 能力別や成果別の賃金上昇
人事評価や実績によって企業が設定した賃金水準に応じて昇給する
3. 職務手当や特別手当の増額
職務内容に応じた手当や、業績に対する報酬などを増額する
昇給に関する注意点とまとめ
昇給には様々なタイプが存在します。定期昇給、ベースアップ、昇格に伴う給与上昇、手当増加など、それぞれ異なる要因があります。昇給がある場合、給与アップの理由を明確にすることが重要です。社員が給与の上昇理由を理解できなければ、昇給の効果が薄れるでしょう。
- 定期昇給: 今後も同様の上昇ペースが続くことが予想されます。
- ベースアップ: 会社の経営状況が良くなれば、賃金がさらに上昇する可能性があります。
- 昇格による給与アップ: 社員のモチベーション向上に寄与します。
昇給が実施される際には、その理由を明確に伝えることで、社員のモチベーション向上や企業への貢献度が高まるでしょう。昇給することが利益を上げる目的だと標榜すると、社員が利益を上げることを自分事と考える理由が生まれます。数字の公開と見える化を使えば、継続した社員教育にもつながります。昇給を小さな会社の戦力的テーマに活用して下さい。